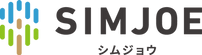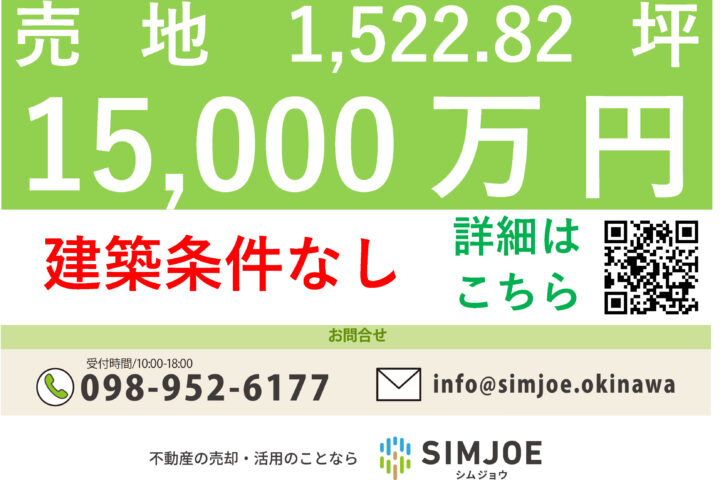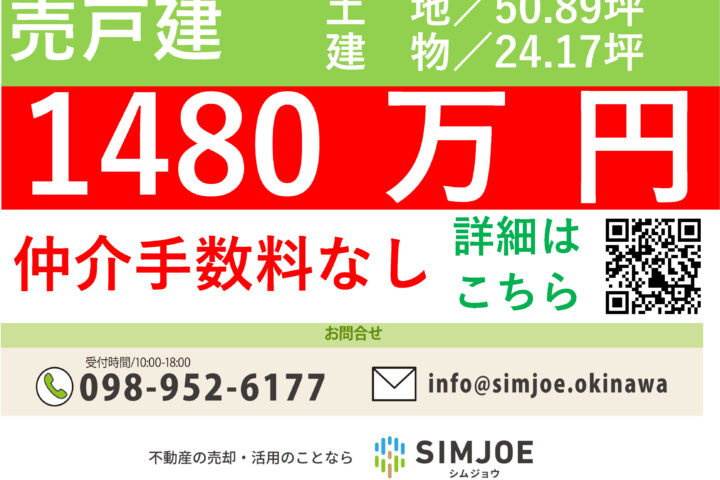沖縄の台風対策の家屋について

南の海で生まれた台風は、日本付近へ張り出している太平洋高気圧の周りを回るように進むので、だいたい沖縄のあたりで、進路を北西から北東の方向へ変えます。そのため沖縄の付近は、ちょうど、台風の通り道になっています。
暖かい海の上の台風は勢力が強くて大きいことや、曲がり角で進むスピードがおそくなることによって、長い時間、大きな影響を与えることがあります。
そのようなことから、沖縄では古くから台風対策で家屋にも様々な工夫を施していました。
石垣や塀
沖縄の家の台風に対する外構の備えとして、最初にあげられるのが、家の周りに屋敷林を植え、さらに石垣で囲う点です。屋敷林には福木(ふくぎ)という木が選ばれることがほとんどです。
屋敷林は福木やヤラボの高木を屋根より高く成長させ、 同じ高さに揃えます。福木は葉が厚く樹幹は太く、根は地中深く成長して風で倒壊しない樹種です 。屋敷林の足元には琉球石灰岩を人の肩ほどの高さに揃えます。

家の周囲に珊瑚や石灰岩などを積んだ石垣やブロック塀を設け、クローズド外構にすることで強固にします。ブロック塀の場合は花ブロックを使用するこで通風も確保できます。
個々の家屋は屋敷林と石垣で四周を取り囲みますが集落に吹き込んでくる強風もあります。その風に対して、複雑にしかし風の力をうまく流すような線形の路地が威力を発揮します。
屋敷林と石垣が風の勢いを弱め、軒の高さに積まれた石垣を抜けてきた風は同じ高さの軒が受けて寄棟へと流れます。住宅はもちろん、地域全体として台風から暮らしを守れるよう、計算し尽くされていたことがわかります
赤瓦屋根
屋根は寄棟にします。こちらの台風は進路によって島に接近し過ぎ去るまでの数日間、風速や風向を変えながら襲来します。
特に過ぎ去る時の「返しの風」は猛烈な風圧となり、痛んだ家屋のとどめを刺すような勢いがあります。

寄棟はどちらの方向からの風にも抵抗しつつ力を流す形です。家が飛ばされないように軒を深くして屋根は大きく、家屋は出来るだけ低く作ることで全体的に風の影響を受けないようにします。最近では水はけや湿気などの問題もあり見られなくなってきましたが、家屋を建てる土地自体も他よりも下がった低い場所が重宝されていました。
そして屋根は重く葺きます。野地竹の上に葺き土を敷均し、赤瓦を載せます。男瓦(丸瓦)と女瓦(谷瓦)を重ねながら組む本瓦葺きですが、その重さは㎡あたり100kgにもなります。 この重さは、寄棟屋根が風圧により吹き上がるのを抑えるためです。そして台風で飛ばされないように漆喰でしっかりと固めています。また赤瓦は放射性能が高く、日没とともに表面温度が急に下がるという効果があるため、日射熱の影響を低減する効果もあります。
昨今の温暖化の影響から台風の進路が変わり、勢力を維持したまま本州へ上陸することも珍しくありません。また近年の異常気象で竜巻の発生も見られます。そのため瓦の飛散対策として2022年1月1日から全国の新築住宅に対して、瓦の固定が義務化されました。沖縄だけの対策ではなくなっています。
防風戸や雨戸
防風戸や雨戸、防風ネットなどの設置は、台風や大雨の対策として有効です。防風戸や雨戸の設置です。昔は木製がほとんどでしたが、膨張・収縮があること、耐久性の問題があることから、今はアルミ製が採用されることが大半です。

近年ではガラスの強度向上やデザイン面などから、沖縄でも新築時に雨戸を付ける家は少なくなっていますが、もちろんですがあったほうが良いと言えます。
台風対策だけではなく、夜間や外出時に雨戸を閉めて窓を開けておくと室内の熱が抜けて熱環境のコントロールができます。
沖縄の家では、「閉じつつ開く」という考え方が大切にされてきました。
後に紹介する「ヒンプン」もその考えから取り入れられたものだと言えます。台風の被害は最小限に抑えつつ、プライバシーを守りながら「閉じつつ」も、最大限風を取り入れて「開く」、蒸暑地域の気候に適した住宅づくりです
防風戸や雨戸がない場合には、窓に防風スクリーンやグリーンネット用のフックやアンカーを付ける家がみられます。台風の接近時にのみ設置できるのでデザイン面でも重宝されています。
これらは安価・簡易に取りつけられるわりに、飛来物が窓に直撃して割れるのを防ぐのに高い効果が期待できます。

沖縄仕様の窓
現代の沖縄の住宅には、最大瞬間風速70m/sを超える台風の風圧に耐える沖縄仕様のアルミサッシが採用されています。
アルミサッシは耐風圧性によってランク付けされていて、国の基準では本州では1階ならS2(風速44m/s相当)とされていますが、沖縄ではS5(風速62m/s相当)が標準です。さらに高層階ではS7(風速76m/s)を使用します。

気密性を高めるために、ダブルロックとなっているのも沖縄のサッシの特徴です
気密性は特に重要となります。高ランクの耐風圧であっても気密性が良くないと台風の時にはサッシは動き、下から水が噴き上がってくることがあります。
台風の風圧は重たいサッシを浮き上がらせ、下の隙間から雨水を噴水のように家の中に吹き込ませます。
ヒンプン
民家へと続く門には門扉がなく、代わりに門の奥に石灰岩などで造られた「ヒンプン」と呼ばれる衝立(ついたて)が配されています。沖縄の古民家でみかける石でできた壁のことです。主に正面玄関の入り口前に設置され外から中が見えないようになっています。

もともとは中国の屏風(びょうぶ)から来ていると言われています。沖縄の古民家は基本的に玄関がなく、広い縁側のようになっているのが特徴で、外から家の中が丸見えになってしまいます。そのため、程よい目隠しとして存在するのがヒンプンです。
目隠しと同時に石垣の間から吹き込む正面の風から建物を防ぐ効果も期待出来ます。ヒンプンは家の中を覗かれないための目隠しでもありますが、それと同時に魔除けの意味もあるそうです。沖縄では「魔物は曲がることが嫌い」という言い伝えがあり、ヒンプンを建てると魔物は曲がってから家に入らなくてはならないので、魔物よけになると信じられてきました。また、頑丈なヒンプンは魔物を跳ね返す効果があると言われています。自然災害などを魔物に見立てることは良く知られています。古来から台風の風に対抗する意味もあったのかもしれません。
耐風性の高い構造
沖縄の住宅は、戦後、木造からRC造の住宅に変わりましたが、これにはやはり台風が大きく影響しています。
戦後、沖縄でも応急的に木造のツーバイフォー住宅が建築されたものの、多湿な風土と合わずに甚大なシロアリ被害が発生しました。さらに1956年に襲来した台風エマは木造住宅に壊滅的な被害を与えました。一方、米軍基地内で建築が進んでいたコンクリートブロック造の住宅は、台風被害が非常に小さく、台風エマを境に木造住宅の着工件数は激減し、RC造の建築が進みました。

そのため、沖縄県の家の約8割をRC造住宅が占めています。昔の木造住宅の材木は細く、接合部も弱かったため耐久性に乏しかった。また、屋根防水施工が不十分で、台風時にしばしば漏水することがありました。そのため木造建築が増えた近年でも木造への不安やRCに対する信頼感からRCを希望する人は多く見られます。
亜熱帯地域の沖縄では台風は身近にある災害として、古くから対策を行ってきました。その長年の経験から生じた知恵と工夫が住宅の建築にはもちろんのこと、生活のなかに自然と根付いています。もちろん全国的に沖縄のような台風対策の建築にすることが良いということではありませんが、その工夫を知ることは個々の災害の対策にも役立つと思います。
最後に台風対策として、一般的に行うことが出来るものを下記に紹介します。
・窓や雨戸をしっかりと閉める
・飛散防止フィルムなどを窓ガラスに貼る
・カーテンやブラインドをおろす
・排水溝や側溝を掃除して水はけをよくする
・鉢植えやゴミ箱など風で飛ばされそうなものを固定したり、家の中へ格納したりする
・停電時に備え、携帯ラジオ、懐中電灯、ローソクなどを用意しておく
・避難が必要になったときに備え、防災グッズや水、食料などを用意しておく
強風や豪雨など普段では見られない台風に不安や恐怖も感じるかもしれませんが
事前に出来ることから準備を行っておくことで、不足の事態を避けることが出来るはずです。
台風に限らず自然災害はいつかやってくるものだと思って、備えておくことが大切だと思います。
記事作成
シムジョウ代表
宅地建物取引士・2級建築施工管理技士
金城 工